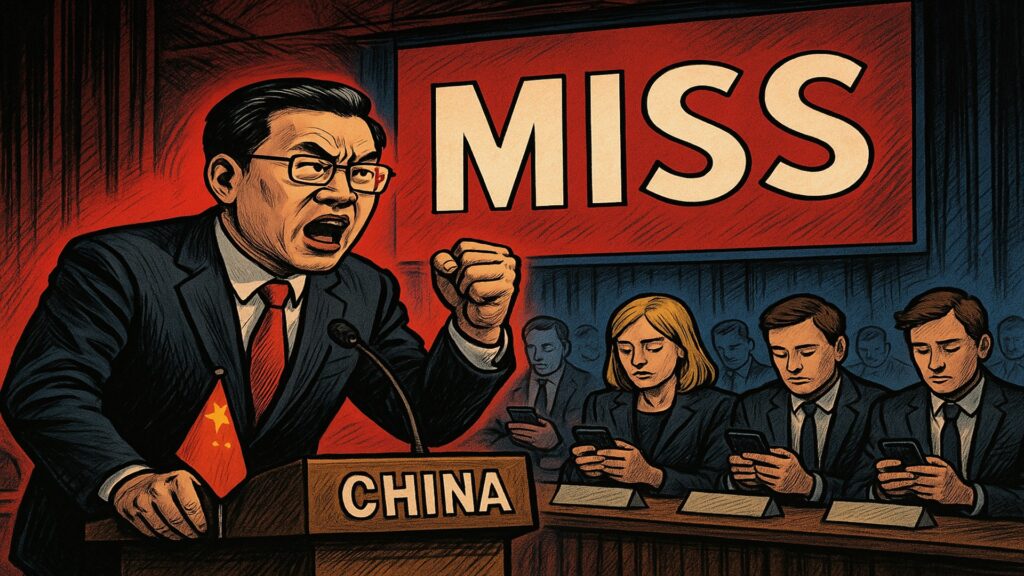2025年11月、中国の薛剣・駐大阪総領事がSNSに投稿した一文が話題をさらいました。「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」。日本のSNSは騒然とし、ニュース番組もこの過激な言葉を繰り返し報じました。
けれども「怖い」よりも「なんか変な日本語だな」などと感じた方も多かったのではないでしょうか?今回は、この“違和感の正体”を丁寧にひもときます。
😟原文は「汚い首」ではなく「汚れた頭」
実は、この発言の原文は「汚い首」ではなく、「汚れた頭」という表現でした。つまり、文字通り“頭”の話です。「砍下」という動詞が「斬り落とす」を意味するため、「首」が訳文に入ってしまったのかと思われます。結果として、「頭を斬り落とす」が「汚い首を斬る」に化け、奇妙な響きになったのです。
日本語で「汚い首」と言われると何を意味しているのか分かりません。腐った脳みそなどと訳したが方が伝わったかもしれません。最初に訳したとされる投稿は削除されているようです。
🤔「一刀砍下」中国語では時代劇的な“決め台詞”
中国語の「一刀砍下」は、古代の処刑や武侠小説でよく使われる“決断と威厳”の象徴です。つまり、「容赦しない」「潔く断つ」という決意表明の一種。中国では「斬る」という表現は必ずしも血なまぐさい意味ではなく、「迷いを断ち切る」など、強い意志を表すこともあります。
薛総領事はおそらく、この“強気の決め台詞”を使って自国民向けに「俺は引かないぞ」というメッセージを発したのでしょう。
😵日本人には「時代劇の悪役」にしか聞こえない
一方で、日本語に直されるとそのまま“殺害予告”のような印象になります。しかも「汚い首」という言い回しは、現代日本語ではほぼ聞きません。結果、真剣な威嚇というより「時代劇の悪役が怒鳴っている」ようなトーンに変換されてしまいました。
日本人にとって「刀で首を斬る」は歴史ドラマや武士の介錯のイメージであり、リアルな脅しとは結びつきません。むしろ、潔い死にざまというようなイメージすらあります。「鉛玉をぶち込む」の方が分かりやすかったのではないでしょうか?
😷“戦狼外交”の一環としての強がり
薛総領事の発言は、いわゆる“戦狼外交”と呼ばれる強硬姿勢の一部です。相手を威圧することで自国のメンツを守る、その戦略自体は一貫しています。とはいえ、外交官が「頭を斬る」と言ってしまえば、言葉のインパクトが強すぎて逆効果。
国内では喝采を浴びても、国外では「品がない」「挑発的」と見られるのが現実です。中国のメンツ文化が、言葉選びのバランスを誤った典型例とも言えるでしょう。
🤪メンツ文化と表現の空回り
中国社会では「強く見せること」=「正義を示すこと」とされる傾向があります。特に公職者は弱腰を見せると「国の恥」と批判されるため、過激な表現を使いがちです。今回の発言も、その“メンツの論理”の延長線上にあります。
ただし、外国語に翻訳されると文脈が切り離され、意図が暴力的に見えてしまう。結果、言葉だけが独り歩きし、「何を言いたいのか分からないけどヤバそう」という印象を残す形になりました。
😴国際的にも“空振り”の演出
アメリカや欧州の報道では、「中国の脅迫外交」「狼戦士スタイルの限界」といった見出しで報じられました。つまり、強気のはずが“滑った”。相手に恐怖よりも失笑を与える外交は、メッセージとして逆効果です。
日本人の多くは、誤訳も相まって、発言の攻撃性よりも、「外交官が低レベルな言葉を使うのか?」という驚きと冷笑を感じたのではないでしょうか。
😫まとめ:国外追放となれば厳しい対応
「汚い首」という言葉は、原文の誤訳と文化のズレが生んだ産物でした。中国のメンツ文化が生んだ“強がりの演出”は、日本人にはただの違和感として伝わったように感じます。そもそもこの発言は日本語ではなく中国語で、中国の国民に向けて発せられたものです。「言ってやった」という国内向けパフォーマンスの側面が強いと言えます。
しかし、言葉選びには品格が表れるものです。せっかくの発言ですから、日本政府は毅然と対応した上で、“言葉の重み”という教訓を共有しても良いのではないでしょうか。
仮にペルソナ・ノン・グラータ(不受容人物)として国外追放となれば、SNS上で一時的に注目を集めるかもしれませんし、中国共産党内で英雄視される可能性もゼロではありません。
しかし実際は、薛氏のキャリアにとっては大きなマイナスとなる可能性の方が高いように思われます。皆さんは、この発言にどのような印象を持ちましたか?