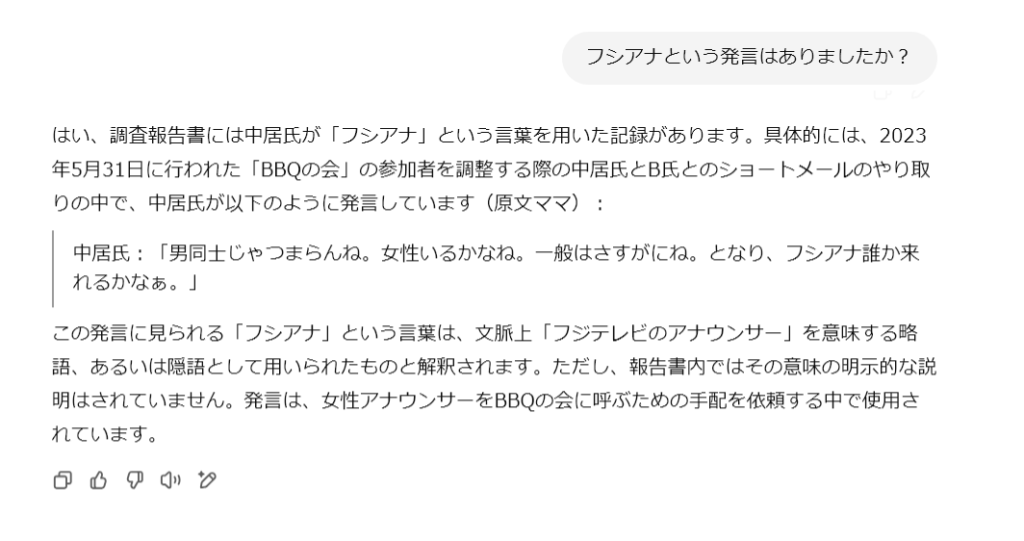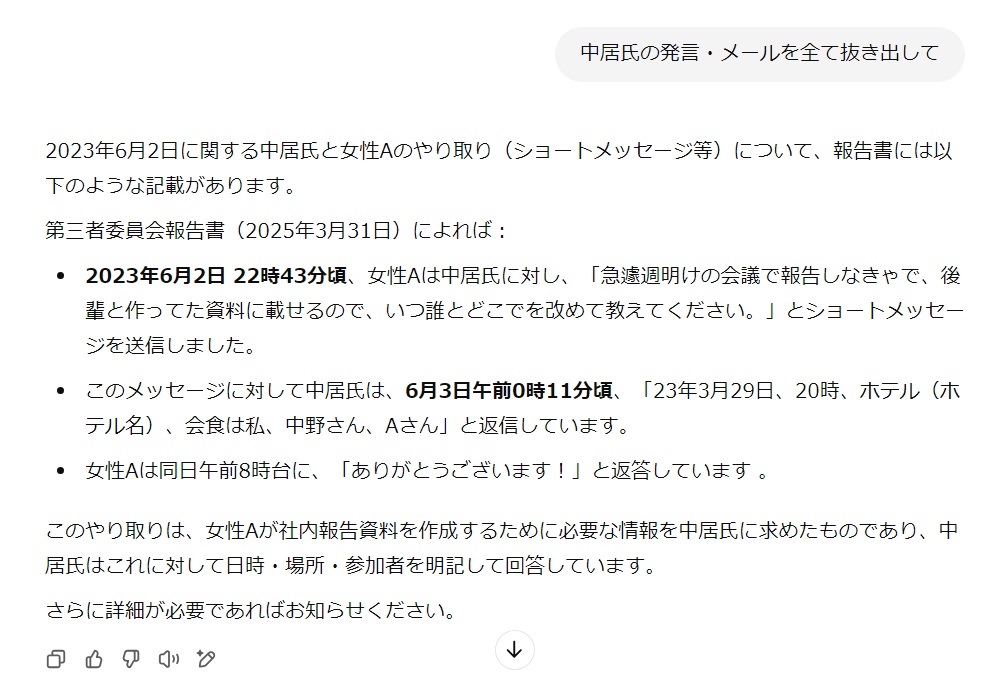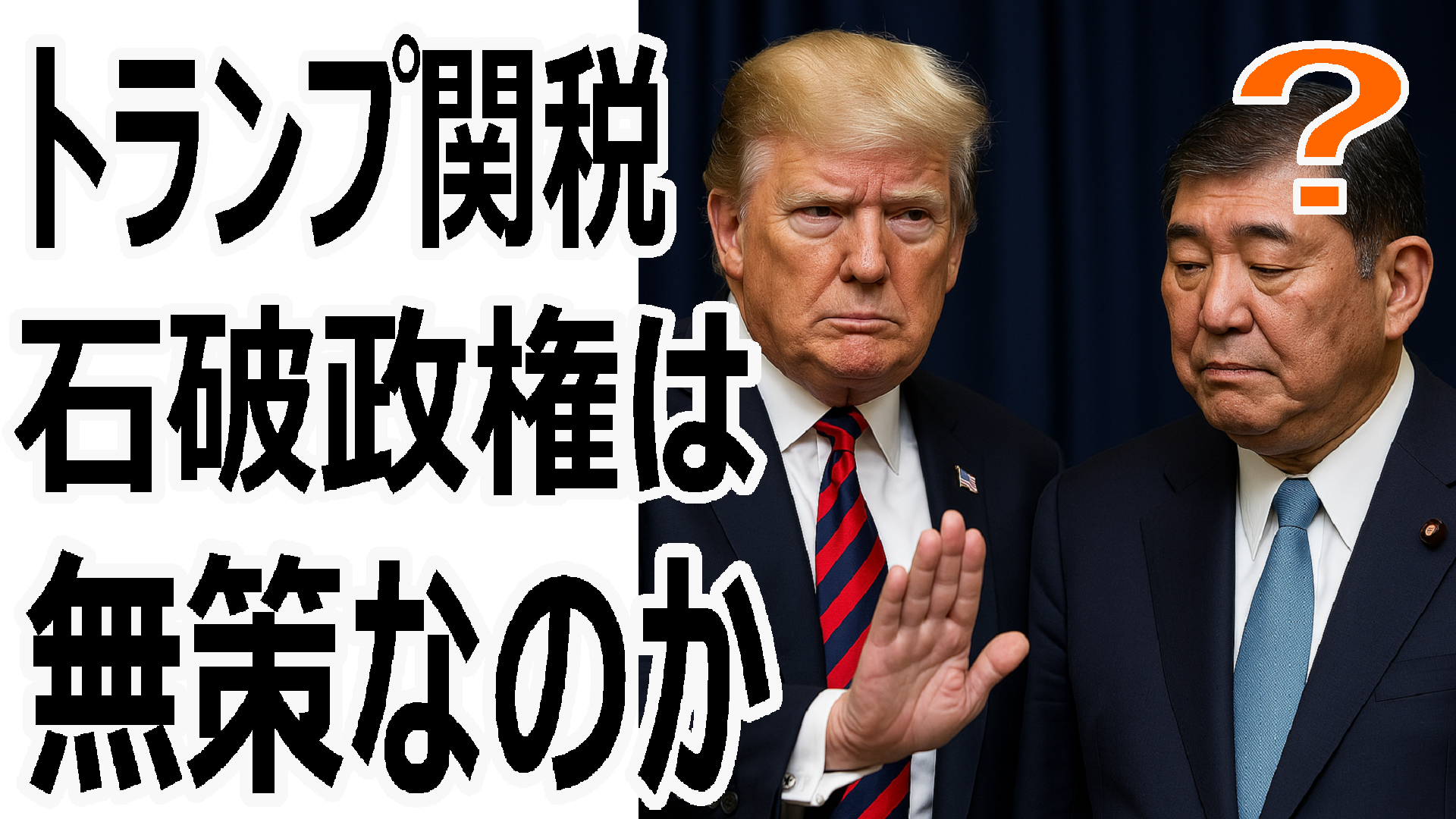フジテレビに関する第三者委員会の報告書をもとに、AI(カスタムGPT)を活用した文書分析の一例を紹介するものです。
筆者は芸能界・報道業界との関わりは一切なく、特定の立場や主張を持つものではありません。あくまで一般の一視聴者として、公開された一次資料をもとに、中立的な視点から情報の扱い方について考えたいという意図です。
昨今、ネット上では切り抜きや部分的な引用のみで情報が広がる傾向があり、必ずしも正確とは言えない内容が拡散されていることも見受けられます。特に動画やブログなどで情報発信を行う方にとっては、信頼性のある情報源を確認し、正しい事実に基づいた意見を発信する姿勢がより一層求められています。
しかし、数十〜数百ページに及ぶ公式文書をすべて目を通すのは現実的に困難な場合も多く、カスタムGPTというAIを活用することで、膨大な報告書の内容を効率よく把握する方法をご紹介いたします。
フジ第三者委員会ナレッジAI
※無料版のChatGPTでも使うことができますが、正確な回答を得るためには、有料版のChatGPTへの加入が求められます。
オリジナル情報:2025.03.31第三者委員会調査報告書
公 表 版、要 約 版、別冊 役職員アンケート結果
なぜ今、報告書を読むべきなのか?
フジテレビに関する第三者委員会の報告書は、企業やメディアの在り方を問い直す重要な資料でありながら、そのボリュームと専門性の高さから、一般読者にとってはハードルが高い文書です。しかし、世の中ではその一部だけが切り取られ、都合の良い情報のみが出回るケースも多く見受けられます。
だからこそ、「正確な情報に基づいた理解」が求められます。
カスタムGPTとは?
カスタムGPTとは、特定の資料や文書を事前に読み込ませ、自分専用にカスタマイズしたChatGPTのバージョンです。読み込ませた資料に関する質問をすれば、AIがその内容に即した形で答えてくれるという特徴があります。
一般的なChatGPTと違い、指定した資料の中から回答を探してくれ、一次資料に即した議論が可能であり、使い方は簡単で、PDFやテキストを読み込ませるだけで作成できます。あとは学習した文章から、返答を作成して返してくれます。
実際の使い方とサンプル
第三者委員会の報告書をテキスト化した上で、カスタムGPTに読み込ませました。そして、このような質問を投げかけました。
「6月2日の出来事を教えて」「中居氏の発言やメールを全て抜き出して」「性暴力と認定した理由を教えて」「女性Aとフジテレビのやり取り時系列で説明して」などです。
すると、AIは報告書本文に基づいて回答を生成してくれました。これにより、全文を読まなくてもポイントを把握することが可能になります。
しかし、AIも万能ではありません。
なお、AIによる回答には十分な注意が必要です。明確に記載されていない内容を勝手に補完してしまうことや、事実無根のオリジナルストーリーを語ることもありました。
不謹慎に感じられる場面もあるかもしれませんが、これはAIの回答を全面的に信じることがいかに危険かを伝える意図であり、あくまで注意喚起の一環としてご理解いただければ幸いです。
このような現象は、AIの生成型モデルには存在するものであり、ハルシネーションと呼ばれます。これは世間一般の情報も同様であり、裏付けのない発言や誤情報を鵜呑みにせず、ファクトチェックを心がけるが必要です。
情報発信者としての責任
特に、YouTuberやブロガー、SNSでのインフルエンサーなど、情報発信を行う立場にある方々には、こうしたAIをうまく活用することが推奨されます。ただし、使い方を誤れば逆効果にもなりかねません。
AIで要点を抽出しつつ、原文にも目を通す、回答を鵜呑みにせず、自分の言葉で検証する、出典や根拠を示すことで、読者の信頼を得ることは必ず行いましょう。
また、コメント欄であっても事実無根の書き込みをすることは、大きな問題となる可能性もあり、また、そのような書き込みで傷つく人がいる可能性も考慮することは共存社会で生きる上で必要であると考えます。
正しい情報を判別すること
情報過多の時代だからこそ、一次資料を適切に解釈することが重要です。カスタムGPTのようなAIツールを使えば、膨大な資料の全体像や要点を素早く把握でき、より正確な情報発信や理解につなげることができます。
AIはあくまで「補助ツール」であり、その出力内容の正確性を最終的に判断するのは人間の責任です。インターネット上には、根拠のない誤情報や意図的に切り取られた情報が多く出回っており、中には大学教授や著名な研究者でさえ、不正確な情報を拡散してしまうことがあります。
混乱の中でウソが溢れている
だからこそ、受け取る情報に対しては常に疑いの目を持ち、信憑性に不安を感じた際には自らファクトチェックを行う習慣が必要です。特に昨今では、中東情勢やウクライナでの戦争、関税政策の影響などにより、国際社会は複雑な混乱を抱えています。日本国内でも、特殊詐欺や闇バイトのように、虚偽の情報に信じ込まされたことで大きな被害を被る事例が後を絶ちません。
今回取り上げた報告書もまた、表面的な報道では見えてこない文脈や思惑が含まれていると感じられます。だからこそ、一人ひとりが情報の背景や根拠を冷静に見極め、正しい理解のもとで判断することが求められています。
情報に対して受け身ではなく主体的に向き合い、AIを含めた技術を上手に活用しながら、正しい情報を手にすることで安全な生活を守ることにつながることでしょう。