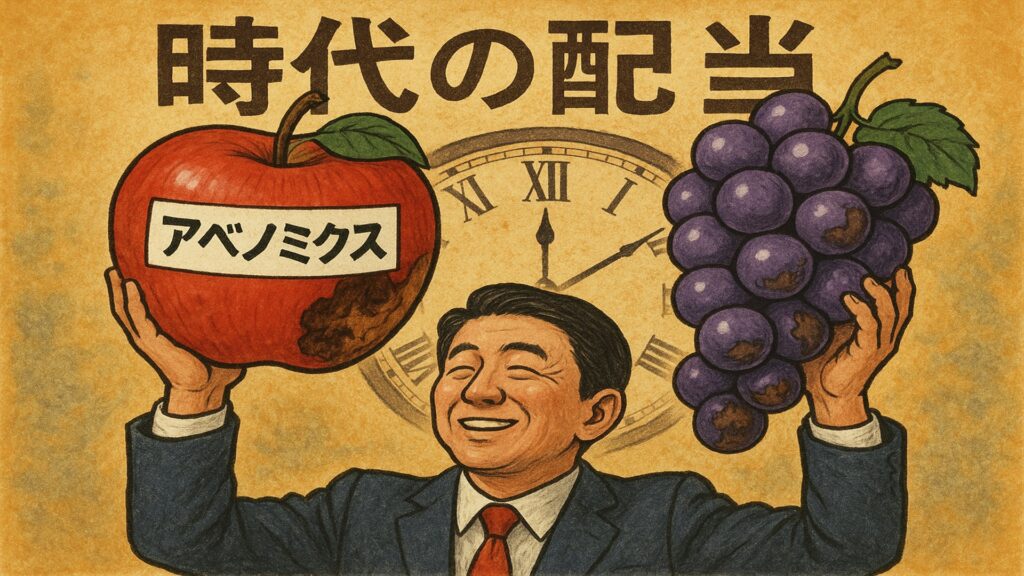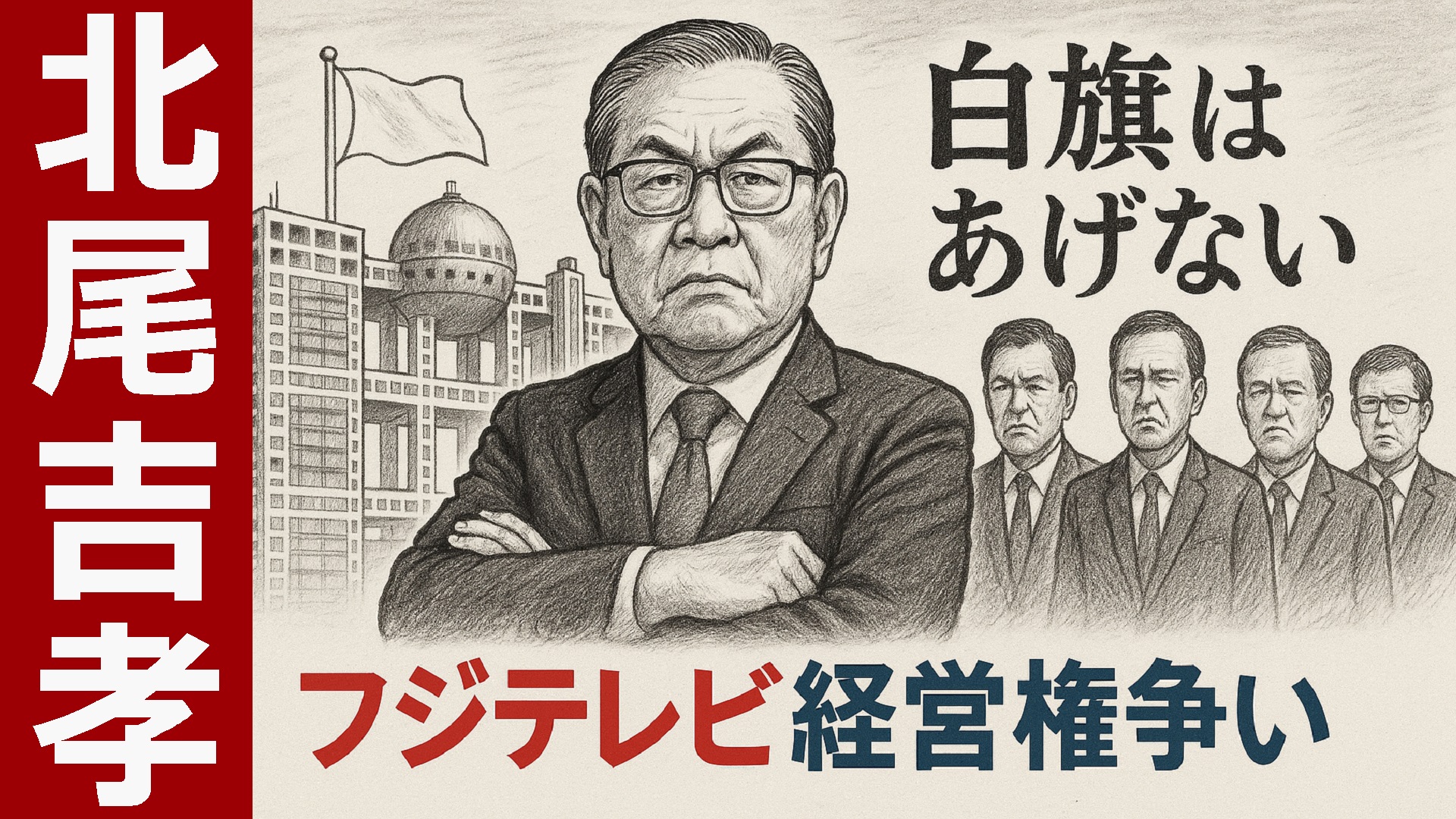オルカンはこの1年で15%の上昇。しかし世界経済の成長は3%程度、インフレも3〜6%に収まっており、実体と株価の乖離は広がる一方です。
経済が追いつかないのに株だけが走る状態は長く続くはずもなく、やがて踊り場や停滞、暴落が訪れる可能性は高いでしょう。特に円高局面では海外資産の価値が目減りし、日経平均も下げやすくなります。
だからこそ今は、ポートフォリオの分散や為替ヘッジといった現実的な対策を整える時期です。勢いに流されて買い急ぐのではなく、暴落や調整も“想定内”にして計画的な投資を続ける——それがこれからの投資家に求められる冷静さなのです。
🤨ニュースの要点:数字が語る“3%と15%”のズレ
株価は先行して走りました。では経済はどうでしょうか。成長率は3%前後で堅実、物価上昇率も多くの地域で3〜6%に収まっています。実体に比べて価格だけが伸びる局面では、その背景を理解しないと揺り戻しに足をすくわれる恐れがあります。この1年を押し上げたのは米大型テックの存在。
将来利益への期待と指数上位銘柄の比重の高さが重なり、資金が流れ込みやすい構造になりました。さらに積立NISAなどのパッシブ資金が自動的に上位銘柄を買い続け、日本の投資家には円安という追い風も加わりました。
ドル建てで+10%でも、円換算で+15%超に見える場面があったのです。つまり「期待 × 自動買い × 為替」という三層が重なり、経済成長率を大きく上回る株価上昇を生んだのです。
😵期待は永遠じゃない:乖離が解消される3つの道筋
永続的に15%の上昇が続くことはありません。株価と経済の乖離は、いずれかの形でならされます。想定されるパターンは三つ。
(1)期待が剥落し急落するハードランディング。主役級の銘柄でも半値近い調整は過去に何度もありました。(2)株価は横ばいのまま数年〜10年かけて利益が追いつき、割高感が薄まるソフトランディング。(3)エネルギー・金融・インフラなど他セクターが相対的に強く、指数全体の下げを吸収する分散吸収型。今の局面はどれに近いのでしょうか。
仮にテックの利益成長が一服すれば、原油価格や資本投資の波によってエネルギーや素材、インフラが再評価される可能性があります。インデックスは“顔ぶれの変化”に弱いように見えても、実際には順応します。指数の顔が変わればトレンドも変わる。そうした可能性を心の片隅に置き、ポートフォリオを“もしも”に備えておくことが安心につながります。
🤔日本の投資家の生命線:為替というもう一枚の盤面
円建て投資家のリターンは「株価変化 × 為替変化」です。たとえばドル建てで年+10%が3年続けば累計+33%になりますが、同時にドル円が150→110と約27%円高に動けば、円換算の増分はほぼ相殺され、トータルで+数%程度しか残らないこともあります。逆に円安は資産の評価額を押し上げますが、新規積立では“高値のドルを買う”形となり効率は低下します。
つまり円安期は守り、円高期は攻め——この切り替えをルールとして持てるかが分かれ目です。
具体的に試算すると、ドル建て+10%が3年で約+33%、為替が27%円高なら円ベースでは+33%−27%≒+6%程度。年率換算すればわずかにプラス程度です。数字は冷静です。だからこそ、為替トレンドを前提にリスクを調節する。ヘッジを使うか、現金比率で吸収するか。計算に当てはめ、自分の“心地よさ”を確かめてみましょう。
😟政策・金利・地政学:為替を動かす3つのハンドル
為替は金利差、政策スタンス、地政学の三つの要因に大きく左右されます。たとえば米国が利下げ志向を強め、日本が段階的に利上げへ進めば、円高に傾きやすいでしょう。逆に世界がリスクオフに傾けば“有事の円買い”が起きやすく、極端な円安には当局の介入が入りやすいのも事実です。だからこそ「円高に振れたらどう動くか」を前もって考えておく価値があります。
また、新NISAで流入した資金はインデックスを通じて需給を下支えしますが、反転局面では“弱い手”として下げを加速させる可能性もあります。過去のバブルや暗号資産の熱狂でも同じことが繰り返されました。積立は続けつつ、リスク許容度に合わせて“売らされない”余力を持っておく——この基本を静かに守りたいところです。
😷アベノミクスの果実は“時代の配当”だった?
この十数年、日本株の上昇と円安のダブル効果で大きな果実を手にした投資家は少なくありません。けれども、その追い風は金利・政策・為替の“時代の配当”でもありました。同じ戦略が次の十年で再現する保証はなく、むしろ環境が変われば逆風に転じる可能性もあります。金利の反転、サプライチェーン再編、地政学の再配置——課題は次々に現れます。
アベノミクス期に便乗して成功体験を得た人も、その手法がこれからも正しいとは限りません。むしろ、その成功例を信じすぎれば、将来大きな痛手につながることもあるでしょう。だからこそ、過去の果実をそのまま未来に持ち込まない姿勢が重要です。ここに、これからの投資の礼節があるように思います。
😴もうひとつの“もしも”:円高が来たら、どこで仕込む?
円高はしばしば怖がられます。しかし、長期の積立にとってはむしろ好機となりえます。過度な円安懸念ばかりに囚われず、「円高が来たら何を、どれだけ、どの順番で仕込むか」を考えておくことが大切です。価格を追いかけるのではなく、迎えに行く姿勢が肝心。メモで十分、数字は大まかでもかまいません。準備している人の手は、いつも静かで早いものです。
あわせて、目標利回り、最大ドローダウン、リバランスの閾値、現金比率など、自分の“基準”を一枚の紙に書き出してみましょう。人に見せる必要はありません。それは自分だけの航海図。良い時も悪い時も、この紙に立ち返ることで軸がぶれません。相場が騒がしいほど基準は力を発揮します。もし今夜少しでも時間があれば、ペンを手に取りましょう。
😍経済3%・オルカン15%の“ねじれ”を、想定内に
最後にもう一度だけ。オルカンが年率15%の伸びを続ける一方で、実体経済(成長率・インフレ・名目GDP)がそれに追随していない状況が長期にわたり維持されるとは考えにくいでしょう。冷静に見れば、どこかで踊り場・停滞・調整(ときに急落)を挟む可能性は高いことは誰の目にも明らかです。
なかでも為替主導の円高は完全には避けにくく、ポートフォリオの分散や為替ヘッジなど“できる対策”は今のうちに整えておきたいところです。それでも円高が進めば海外資産の円換算価値は目減りし、日経平均も弱含む局面があり得るでしょう。
だからこそ、こうした展開を“想定内”にするための準備が肝心です。勢いに任せて買い急ぐのではなく、調整局面を前提にした計画的な投資を続けましょう。ジョージ・ソロスは「市場は常に誤っている」と言っていますが、今が大間違いである可能性も頭の片隅に置いておきましょう。