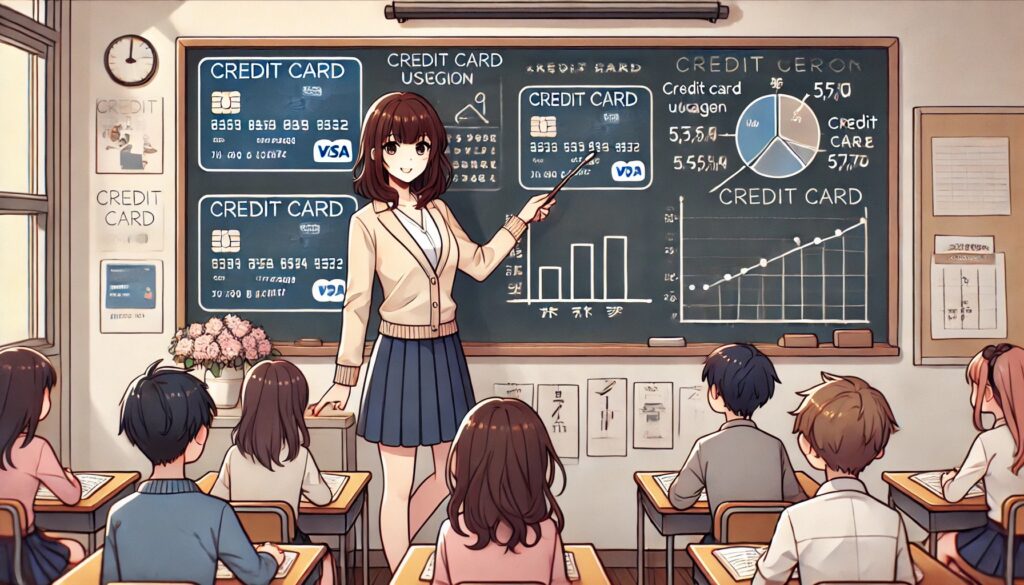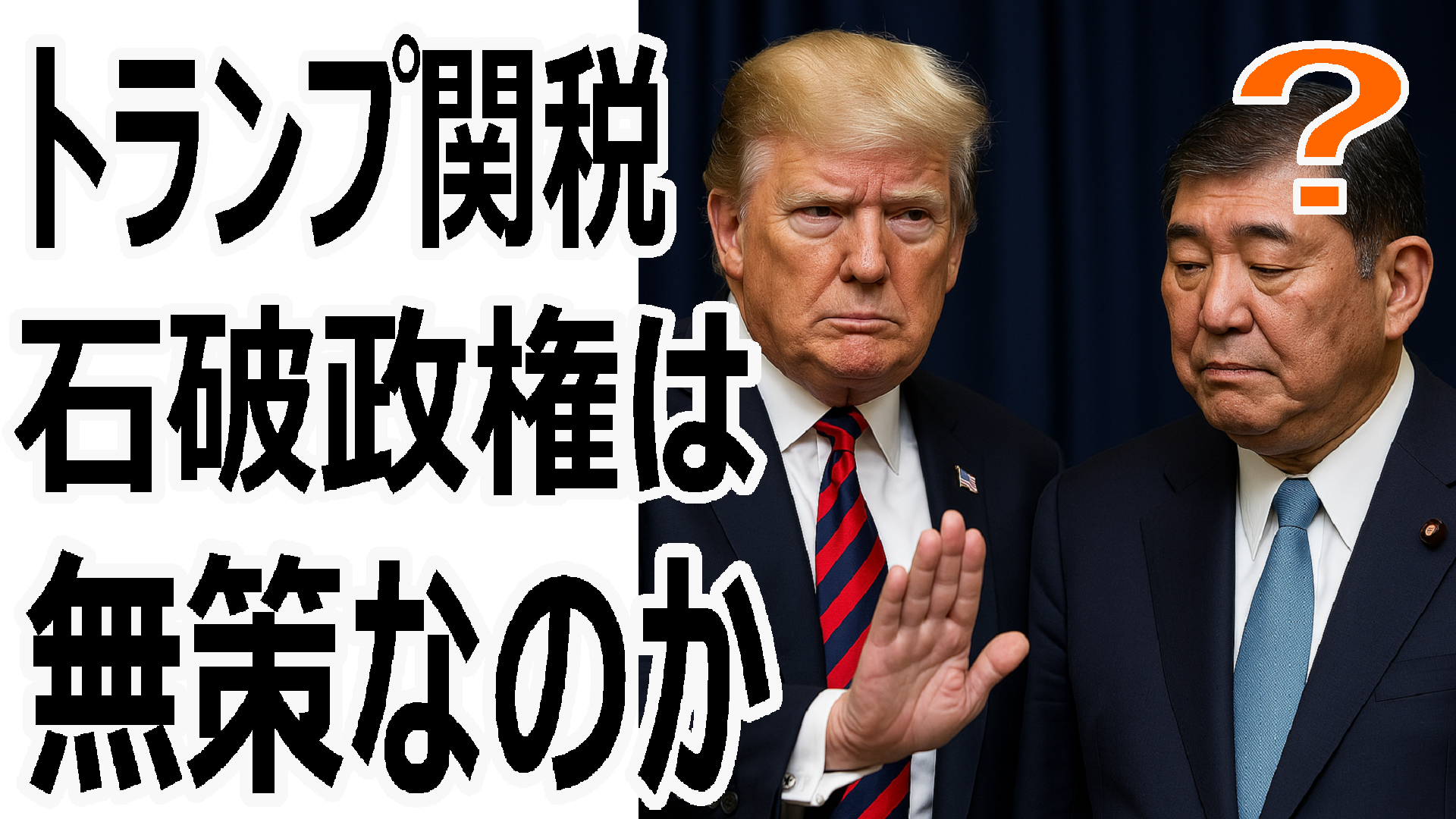最近「リボ払いにするとポイントプレゼント!」という広告を目にする機会が増えました。一見するとお得に見えるこの仕組み。しかし、その裏側には、毎月静かにお金を吸い取られていく”無限のサブスク”のような構造が隠されています。この記事では、リボ払いがなぜ危険なのか、無限に金利が膨らむ仕組みを考えていきます。
リボ払いは本当にお得なのか?
リボ払いは、毎月の支払い額が一定になるため、一見すると「家計が安定する」と感じるかもしれません。しかし、実際には借入残高に対して年15%から18%という非常に高い金利がかかっており、支払った金額の大部分が利息(または手数料)として消えていきます。
例えば、100万円を年利18%でリボ払いにした場合、仮に月の返済が1万円だとしたら、最初の月の利息は約14,794円になります。つまり、1万円払っても元本は1円も減らず、逆に借金が増えるのです。この状態が続くと、完済は不可能になります。
払っているのに借金は減らない
ここで問題なのは、仮に金利が少し低い年利12%程度であっても、同じような現象が起きることです。100万円の借入に対し年12%の利息が発生する場合、1ヶ月の利息は約9,863円になります。ここでも、月1万円の返済では、元本はほとんど減らず、延々と利息を払い続けるだけの構造になるのです。
つまり、リボ払いは「元本を減らす返済」ではなく、「利息を払い続けるサブスクリプション」のようなものと言っても過言ではありません。
なぜこの高金利が見えにくいのか?
通常のローン契約であれば、金利や返済期間、総支払額が明記され、契約前に内容をしっかり確認できます。しかし、リボ払いはあまりに簡単に始められます。カード利用後に「リボに変更するだけでポイントがもらえる」といった軽い誘導で、スイッチを入れた瞬間に高金利ローンが始まってしまうのです。
小さく表示される金利表示の落とし穴
しかも、契約画面の片隅に小さく「手数料年率18%」と書かれていても、その意味をしっかり理解している人は少ないでしょう。総額でいくら支払うのか、完済まで何年かかるのか、そうした重要な情報は利用者の目に触れにくい仕組みになっています。
このような設計は、ユーザーに「借金をしている」という意識を持たせないまま、高金利を課すという点で非常に危険です。
無知な人から静かにお金を奪うビジネスモデル
リボ払いは、利息制限法で定められた上限ギリギリの金利設定がなされているケースが多く、非常に高金利な商品です。これは、知識のない利用者が「自分で選んだ」と見なされ、結果として高金利に苦しむことになる、非常に不公平な構造です。
金利は変動する
また、日本銀行がマイナス金利政策を解除し、政策金利を引き上げる動きを見せている現在、一般のローンや住宅ローンの金利もじわじわと上昇しています。それでもなお、リボ払いの金利は据え置きか、さらに高止まりしている状況です。経済環境と無関係に、常に消費者から最大限のお金を吸い取る設計になっているのです。
サラ金というビジネス
高利貸しという言葉も使わなくなりましたが、その前はサラ金と呼ばれていました。ウシジマくんのような闇金ほどの高金利ではありませんが、住宅ローン金利や車の金利に比べれば、はるかに高い金利が乗っかり、返済総額は大きく増えることを注意しましょう。今のリボ払いは、名称が変わっただけで本質は変わっておらず、名称が柔らかくなったとしても、実態は高金利でお金を貸すビジネスに他なりません
まとめ:リボ払いは「見えない地獄」
誰もが簡単に使える便利な機能のように見えるリボ払い。しかし、その実態は「金のない人からさらに金を吸い上げる無限サブスク」のようなものです。
借金自体を完全に否定するわけではありません。目的が明確であり、返済計画が立てられているなら、ローンは有効な手段にもなり得ます。しかし、リボ払いのように、元本が減らないまま手数料だけを払い続ける構造は極めて危険です。
目の前の数百ポイントの誘惑に負けて、将来何十万円もの支出を抱え込まないようにしましょう。リボ払いという見えない借金に、どうか巻き込まれないでください。
借りるなら短期返済
お金は、自分が持っている範囲で使う。足りないなら、まず生活を見直す。それでも必要なら、正規の契約を経て、まともな金融機関から借りる。そういった基本的な金銭感覚を持つことが、私たちを守る唯一の手段です。
確かにこの手の高利貸しは、簡単に借りることができ、お手軽です。短期的に必要な金額を借りるのであれば、便利な使い方ですが、短期的な少額利用に限るべきであり、常態化や多額の借入は避けるべきでしょう。