2025年10月、自民党と公明党の長年にわたる連立が解消されました。表向きの理由は政治資金問題とされていますが、その背後には政策上のすれ違いがあった可能性があります。高市早苗総裁が掲げた「外資による土地取得の厳格な規制」や「メガソーラー開発の見直し」は、公明党が重視してきた「共生」や「経済活性化」とは異なる方向性を持っていたとも言われています。表面下で進んでいたこの温度差が、最終的に溝を深めたのかもしれません。公明党が連立を離れる判断を下した背景には、単なる政局以上の事情があったとも考えられます。
😂高市政権の外資規制とメガソーラー見直し
高市政権の特徴として、経済安全保障の強化を掲げた点が挙げられます。自衛隊基地周辺や水源地での外国資本による土地買収への懸念を受け、「重要土地等利用実態調査法」の改正が検討されました。事前審査や利用制限の強化を目指す動きは、国内の安全保障意識の高まりを背景に一定の理解を得たとされています。また、再生可能エネルギー、とくにメガソーラー事業に関しても、環境への影響や中国製パネルへの依存が問題視されてきました。高市氏が求めた環境アセスメントの厳格化は、こうした課題に対応する一環だったとみられます。ただし、これらの方向転換は、公明党が掲げる「地域共生」や「民間活力の活用」とは一部で相反し、政策的な距離が広がっていった可能性もあります。
🤔森林伐採と中国製パネル
森林を伐採して太陽光パネルを設置するという行為には、環境とのバランスを欠くとの指摘があります。環境省の試算では、2024年時点で全国のメガソーラーの約3割が森林伐採を伴っており、中国製パネルの占有率も高いとされています。再生可能エネルギーの推進が必ずしも自然保護と両立しない現実が、政策議論の焦点になりつつあります。固定価格買取制度(FIT)によって支えられた再エネ事業の負担が国民の電気料金に反映され、海外企業に利益が流れる構造も議論を呼びました。こうした中で、メガソーラー開発を見直そうとする高市政権と、共生重視を掲げる公明党との間に温度差が生じたと考えられます。
😟国交省の限界と、公明党が抱えたジレンマ
公明党が長年重視してきた国土交通大臣ポストは、土地利用や開発許可に関わる重要な役職でした。しかし、森林法や農地法、環境アセスメント制度などの権限が他省庁にも分散しているため、国交省だけで政策の方向を変えることは難しかったとみられます。高市政権のもとで、内閣府や環境省、農林水産省が連携して規制を進める動きが強まり、公明党の影響力は限定的になっていった可能性があります。結果的に、公明党が閣内で政策を主導する余地が狭まり、存在感を維持するのが難しくなっていったとも推測されます。
😴「連立に残る」か「メンツを守る」か?
政権内での発言力が低下し、政策上の立場も通りにくくなる中で、公明党は連立離脱という選択肢を模索した可能性があります。表向きは政治資金問題が理由とされましたが、背景には政策的な違和感があったとの見方もあります。「このままでは自民党の一部として埋没してしまう」という危機感があったのかもしれません。結果として、連立離脱は“逃避”というより“独自性の再確認”を目的とした判断だったとも考えられます。強引に見える決断も、党としての存在意義を守るための一手だった可能性があります。
😵中国との関係と国際的プレッシャー
公明党は、創価学会を支持母体とする平和外交路線の延長で、中国との関係を重視してきたと言われています。2025年10月の離脱前には、中国大使と斉藤鉄夫代表が会談し「経済協力の継続」を確認したという報道もありました。表向きは外交儀礼の一環にすぎないとされていますが、高市政権の対中姿勢との温度差が浮かび上がった形です。国内世論が「外資規制」や「経済安保」を支持する傾向を強める中で、公明党の“共生”メッセージが響きづらくなっていたとも考えられます。また、高市氏が南モンゴルの人権問題に触れた発言が中国側に敏感に受け取られたとの見方もあり、いずれも推測の域をでませんが、複雑な国際環境が党の判断に影響した可能性もあります。
😁公明党の再出発
高市政権は2026年にかけて、土地取引の事前審査義務化や環境アセスメント基準の再設計、FIT制度の縮小といった制度改革を進めるとみられています。これらの改革は地方自治体や事業者に影響を与える可能性がありますが、国民の安全保障意識の高まりを背景に一定の支持を集めているようです。一方、公明党は野党として「地域共生型再エネ」や「外国人との協働」を掲げ、与党時代とは異なる立場から再出発を模索しています。連立離脱によって政策面の自由度は増したものの、長年の影響力や安定した地位を失ったことは否めません。今後は限られた議席の中でどのように存在感を保つかが問われるでしょう。議席数や支持基盤の変化によって、党の方向性が再び問われる可能性もあります。
🤔まとめ|政治の“現実”をどう見るか
公明党の連立離脱は、単なる政局というよりも、政策上の優先順位や理念の違いが表面化した結果だったとの見方もあります。高市政権が進める外資規制やメガソーラー見直しは、国益や安全保障の観点から一定の評価を受ける一方、公明党の「共生」理念とは整合しづらい側面があったのかもしれません。背後に中国がいるなら政権に残って妨害したはずなどと擁護する意見もSNSでは見受けられますが、高市総裁の政策を止められなかった可能性が高いとみられます。悪い言い方をすれば、追い出される前にメンツを保つために離脱したという見方も一部で語られています。両党の関係が今後どう変化するかは不透明ですが、今回の離脱は日本の政治バランスに少なからず影響を与える出来事となりました。政治とは理想と現実のせめぎ合いであり、その中でどのような判断がなされるのか、引き続き注視していく必要がありそうです。










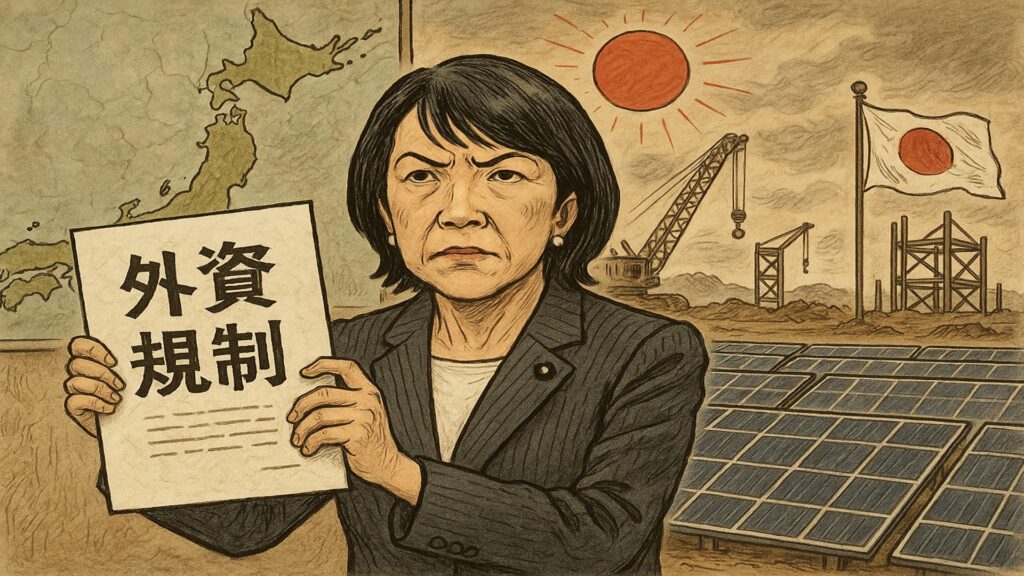
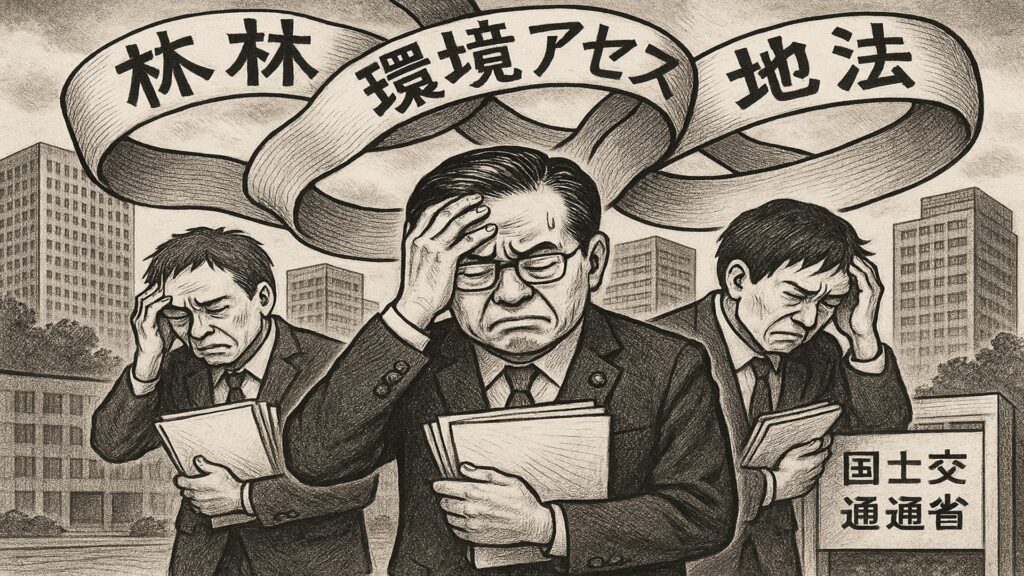

.jpg)
