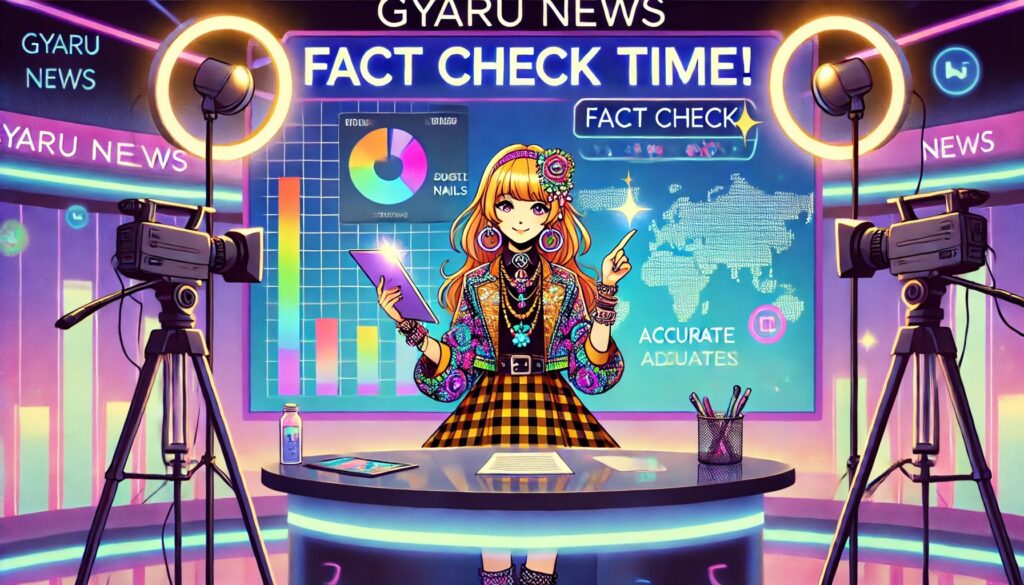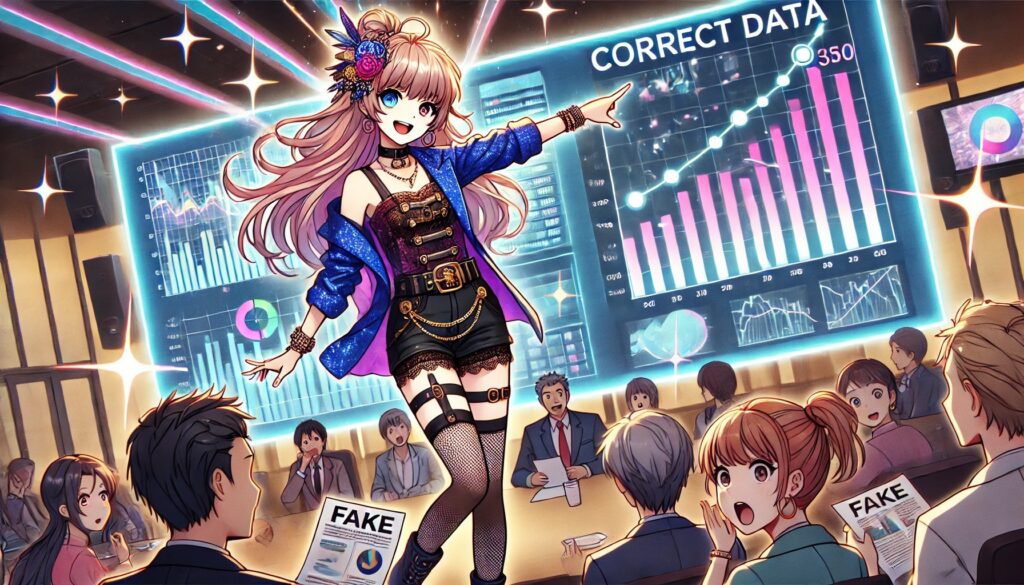「子どもを育てたくない若者が52%」という衝撃的な見出し。けれど、その数字、本当に信じていいのでしょうか?偏向報道が絶えないオールドメディアの意図された印象操作にまんまと乗せられてしまうかもしれません。その情報は本当に正しいですか?
不思議な4択と子どもあり15.9%の謎
3月22日に公表された、子ども・子育て支援法改正案に関する意識調査の一部がSNS上で大きな波紋を呼びました。特に「10代後半から30代前半の男女で52%が『子どもを望んでいない』と回答」という見出しが、少子化の深刻さを煽る形で拡散されました。
不自然な4拓
しかし、この調査結果の裏側を冷静に見ていくと、いくつかの違和感が浮かび上がってきます。まず、選択肢は、1.子どもはおり子育てしている。2.子どもはいるが育てていない。3.子どもはいないが子どもを育ててみたい。4.子どもはおらず、子どもは育てたくないの4つのみでした。
一見すると網羅的に見えるこの4択ですが、結婚相手がいない、経済的に厳しい、今は考えていない、もうあきらめた、まだわからない、といった現実的な状況を示す選択肢は含まれておらず、「子どもが欲しくない」という回答が多くなる構造になっているようにも感じます。
統計と一致しない
さらに不思議なのは、全年代の結果を見たときに「子どもがいる」と回答したのが、わずか15.9%しかいなかった点です。国勢調査などの人口統計・結婚率・出産率の実データを積み上げると、39才の女性は50%以上が出産していることが事実であり、人口分布に沿ったアンケートであれば、仮に15才からであっても、20から30%の女性は出産を経験している計算になります。
このアンケートは、男女合算ですので、父親を含めれば、40から50%の人に子供がいることになります。このアンケートの母集団構成や実施方法など詳細が公表されていないため、正確な検証は困難ですが、例えば対象が若年層に偏っていたり、質問の内容を意図的にすることで、このような結果にすることは難しいことではありません。
RehacQで指摘されたアンケートの課題
この調査結果について、「RehacQ(リハック)」が生配信されていました。
司会の高橋弘樹氏は、15歳から調査対象としている点に疑問を呈し、「その年代ではモテることしか考えていない人も多く、将来のことを真剣に考える段階ではない」とコメント。さらに、黒岩里奈氏も「結婚できない年齢の人を対象にしているのはいかがなものか」と、対象年齢の選定そのものに問題があることの指摘もありました。
15才に子育ての疑問
また52%の中に潜在的に子供は欲しいが、何かしらの問題で持つことが出来ない人が含まれているのではないかという指摘に対して、末富教授は、2割くらいは、子供はいらない少子化対策も必要ないという人がいると思われると発言しています。
黒岩里奈氏は子供を持たない夫婦共働きのDINKsではありますが、以前とは違い、現在は子供を作ることに前向きになっているという話もしており、出産はするが、子育ては夫が行うなどと言う話などもありました。20代では子供を作る予定はなかったが、30代になると子供を産むことを考える例になっていると思います。
教授は微妙にオモロイ
4択の選択肢に関しては「4拓でたまったま聞いたんですよ」や、他にも「ショックすぎて胃腸炎になった。」「日本大学は、大変子育てを応援する大学なんです。世の中的にイメージ悪いと思うんですけど」などと自虐的なことも発言するなど、微妙な面白さがあります。
他にもRehacQらしい内容が多々ありますので、合わせてご覧いただくことをおススメします。

アンケートを鵜吞みにしない力を
今回のような意識調査は、統計情報とは異なり、設問の作り方や選択肢の出し方によって狙った結果を導くことが可能です。調査方法が不適切であれば、得られた結果も歪んだものになりかねません。
また、メディアが「〇〇%がこう答えた!」と大きく取り上げたからといって、それが必ずしも社会全体の実態や真意を表しているとは限りません。報道はしばしば“インパクト重視”で構成されるため、元データの背景や調査設計を見ずに信じ込むのは危険です。
メディアによる誘導
このようなメディアの誇張報道は、視聴者の関心を煽ったり、再生数や視聴率を稼ぐことを目的としているように見受けられます。都合の悪い事実には触れず、インパクトのあるデータだけを強調して、話題性を優先した番組構成が目立ちます。このような手法では、毒舌系コメンテーターが過激な発言を繰り返し、最後はお決まりの政府批判という展開が多く、視聴者の思考を一方向に誘導しかねません。
ネガティブな思考への誘導
このような偏ったデータが示されることで、若者の半数が「子どもを育てたくない」と誤解してしまい、あたかも少子化が不可避であるかのようなイメージが形成されてしまう可能性があります。統計の見方を知る人であれば、「子どもあり」がわずか15.9%という結果に強い違和感を覚えるはずですが、そうした視点を持たない人々にとっては、「自分も子どもを持たないほうが自然なのかもしれない」といった思考に誘導されかねません。
ミスリードを誘う
このような“ミスリード”とも言える情報の氾濫によって、若い世代が将来に対してネガティブなイメージを抱いてしまうことは、極めて深刻な問題です。分かっていながら、それを報じるマスメディアも、話題性を優先し、背景の検証を省いたまま拡散してしまうケースが少なくありません。少子化対策の一環として、このような情報を拡散するマスメディアに対する規制や検証機能が必要ではないでしょうか。
まとめ:疑問があれば、AIにも調査を依頼してみよう
もし調査結果に違和感を覚えたなら、専門家に意見を聞くのも良いですが、最近ではAIに質問して裏付けを取ることも可能です。昨今の生成AIでは、複数の情報からその信ぴょう性を調べるような機能があり、この情報は本当に正しい?などと聞けば、様々な角度から調査をしてくれます。
また、推論なども進化しており、このようなアンケート結果はあり得るの?などと聞けば、情報を分析して、内容が正しいかをチェックしてくれることもあります。ただし、これも過度な信用は禁物です。今回のように大手メディアが同じ情報を発信するとそれが間違っていたとしても、全てのサイトで間違った報道をしていれば、それを訂正することはできません。
AIは不足分を補うが過信は禁物
このようにAIを活用することで、調査の背景や選択肢の妥当性、他の統計との比較などを素早く確認できます。情報があふれる現代社会では、意図的なミスリードや誘導が潜んでいることも少なくありません。従来のメディアに依存するだけでは見抜けなかった情報の裏側も、今では個人の手で調べることが可能です。
だからこそ、目にした情報をそのまま受け入れるのではなく、「なぜこういう結果になるのか」「他のデータと整合性はあるか」と疑問を持つ姿勢が大切です。私たち一人ひとりが、自分の頭で考え、情報の意味を見極めること。それが、ミスリードに流されない社会を築くための第一歩になるのではないでしょうか。