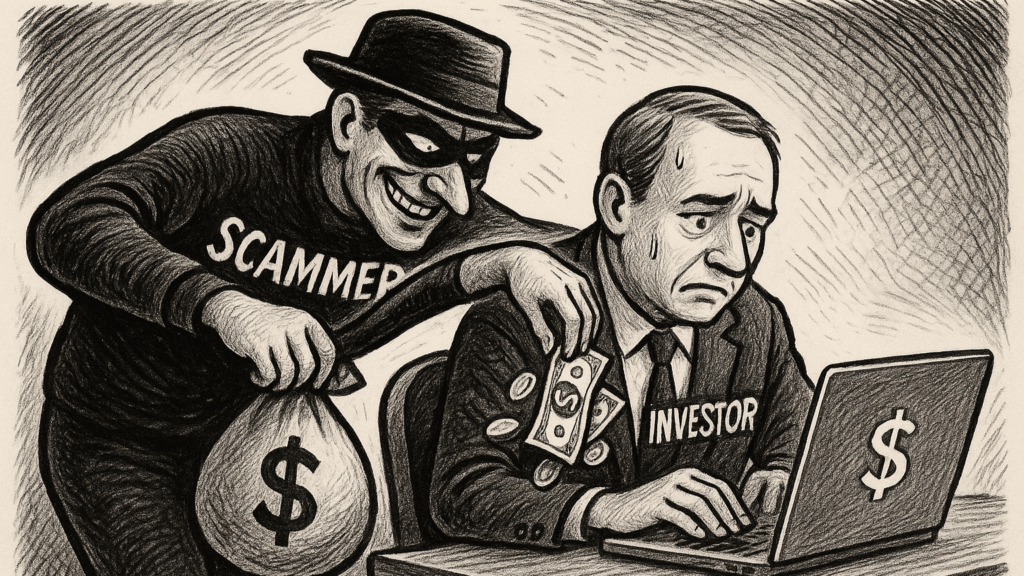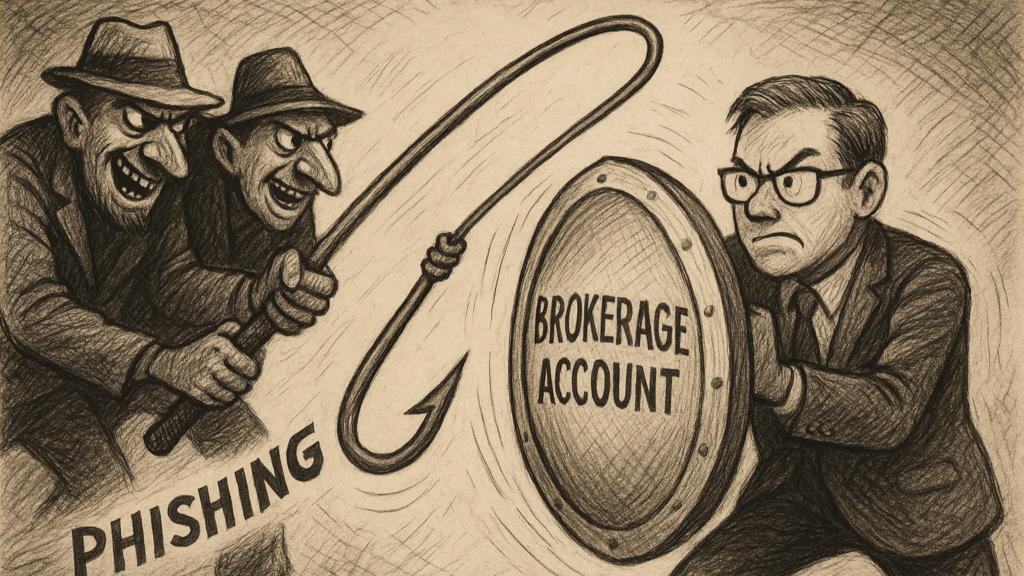近年、インターネットを利用した金融取引が一般化する中、証券口座を狙ったサイバー犯罪が深刻化しています。特にフィッシング詐欺の手口は年々巧妙さを増しており、偽のログイン画面や本物そっくりのメールを通じて個人情報を盗み出し、預かり資産を不正に操作されるケースが相次いでいます。ひとたびログイン情報を奪われれば、資産はあっという間に移動・消失し、被害に気づいた時には取り返しがつかない状況になっていることも珍しくありません。本稿では、実際に発生している被害の傾向と具体的な詐欺の手口、そして資産を守るために個人が講じるべき実践的な対策について、最新の情報を交えて解説します。
被害の拡大と手口の変化
現在、証券口座の乗っ取り被害が急増しており、2025年1月から4月末までの不正取引額は約3,049億円に達し、被害件数は3,505件に上っています 。主な手口は、フィッシングメールを通じてログイン情報を盗み取り、保有株を無断で売却し、その資金で中国株を大量に購入するというものです 。さらに悪質なのは、ハッキングした口座で小型株を購入し、別の証券会社で売却して利益を得るという手法です。被害者の口座には、値下がりして大幅な損失が出た株が残されており、損だけが残る形になります。
中国株を利用した新たなスキーム
多くの証券会社が中国株の取引を一時停止していますが、これは中国株に限らず、どの国の小型株でも同様の手口が再現可能です。このような手法は、従来の「別の口座に現金を移す」タイプの不正とは異なり、アラートが出にくく、本人確認も不要で、犯人は別の国からでも簡単に操作できるという点が特徴です。中国株を利用する理由は、乗っ取られた日本の証券口座で中国株を購入し、中国側の証券会社で売却して利益を上げる──という資金移動のスキームが使えるためと考えられます。
証券業界の対応と補償制度の動き
被害が拡大する中、日本証券業協会は大手証券やネット証券10社と協議し、不正アクセスによる顧客被害に関する一定の補償を行う方針を明らかにしました 。補償方針を表明した証券会社には、SMBC日興証券、SBI証券、大和証券、野村證券、松井証券、マネックス証券、みずほ証券、三菱UFJeスマート証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、楽天証券が含まれます。
また、証券会社を名乗るフィッシング詐欺メールも出回っており、公式窓口に問い合わせるなどの慎重な対応が求められています 。このような状況を受けて、証券会社各社はセキュリティ対策の強化を進めており、ログイン時の多要素認証の必須化や、フィッシング詐欺に対する注意喚起を行っています。
メールの特徴と危険なポイント
例1「SBI証券 <リンク> セキュリティ環境に関するお知らせ 平素、証券サービスを定期的とした第三者による不正利用やアクセス攻撃が多数報告され ております。お客様の資産を安全に守るためにも、現在のご利用環境を確認・把握する取り組みを推進しております。」
例2「平素よりSBI証券をご利用いただき、誠にありがとうございます。 近年、金融機関を装ったフィッシング詐欺や第三者による不正アクセス被害が急増してお り、これに伴い、証券各社および日本証券業協会においてセキュリティ対策の強化が求め られています。 当社ではこの状況を踏まえ、お客さまの大切な資産を守るため、2025年5月31日(土)を もって、以下の対応をすべてのお客さまに義務付けることといたしました。」
偽装メールの構成と心理誘導の手口
メールの差出人名は「SBI証券」と記載されていますが、実際のリンク先URLは、SBI証券とは無関係の不審なドメインです。メールの末尾には、「株式会社SBI証券、金融商品取引業者、登録金融機関、住所」など、実在の企業情報が記載されており、信頼感を偽装する手法がとられていますが、この手の情報は誰でも知りえるものです。本文では「デバイス認証が必要」「補償制度の適用条件」など、不安を煽る文言が繰り返されていたり、「不正アクセスが増えています」「設定しないと補償されません」などの“焦らせる表現”は、冷静な判断を奪う典型的な詐欺の常套手段です。
宛名がない=危険なメール
証券会社や銀行からの重要なメールには、通常、冒頭に「〇〇様」などの宛名が明記されているのが一般的です。特に、口座情報の変更や取引確認、補償制度に関する通知など、重要な個人向け連絡であれば、個別の宛名が含まれます。これは、信頼性の担保と、正当な顧客宛であることを示すための基本的な配慮です。
一方で、「お客様各位」というような宛名のないメールは、一斉送信型の迷惑メールやフィッシング詐欺である可能性が高くなります。特に金融機関を装った詐欺メールでは、個別の宛名を省略し、一般的な呼びかけで不特定多数に送信することで、広く情報を取得しようとする傾向があります。
したがって、宛名がない時点で、そのメールは詐欺であると疑うべきです。ただしセミナーの案内など、個人宛でない場合は、その限りではありません。
専用メールアドレスによる防衛
金融系のサービスでは、Yahoo!やGmailのエイリアス機能を活用し、専用のメールアドレスを使うことが非常に有効です。たとえば「[email protected]」のように、証券会社専用のメールアドレスを設定しておくことで、そのアドレス以外に届いた証券会社からのメールは全て迷惑メールであることが明確になります。
普段使いのアドレスを金融機関に登録しないことで、万が一情報が漏洩したとしても、他のサービスへの影響を抑えることができます。また、証券会社からの通知をその専用アドレスで一括して受け取るようにすれば、重要なメールを見逃すリスクも減り、管理も格段に効率化されます。
さらに、メールソフトやサービスにはアドレスごとに色分け表示やラベル付けが可能な機能もあるため、それらを併用することで視認性を高める工夫も可能です。このように、専用のメールアドレスを活用することは、日常的なセキュリティ対策として非常に実用的で効果的な方法なのです。
ドメイン確認は危険
「ドメインを確認すれば偽物かどうかわかる」と言われることもありますが、実際にはドメインも非常に巧妙に偽装されており、ITの知識がない方が正確に判別するのは極めて困難です。むしろ、本物に酷似した偽ドメインに騙されるリスクが高まります。そのため、ドメイン確認に頼りすぎるのは危険です。
特に最近の詐欺メールでは、正規のドメインに酷似したもの(例:@sbi-sec-support.com、@sbi-sec.co、@sbi-sec-jp.com)を用いる場合もあります。他にも小文字のLと大文字のI、数字の0とアルファベットのOというような紛らわしい文字、日本語の全角文字を使って、本物と見分けがつかないような表示にする手法もあります。
つまり、メールの一見「安全そう」に見えるドメインであっても、そこをクリックすることで詐欺サイトに接続されてしまうリスクがあります。したがって、ドメインだけで判断するのではなく、そもそもメール内のリンクをクリックしないことが重要です。
電話連絡のケースにも注意
例えば、「〇〇証券」を名乗る人物から留守番電話が入り、「至急折り返してください」との伝言が残されていた場合でも、そのまま留守電に記載された番号へ折り返すのは危険です。
適切な対応としては、該当する金融機関の公式の代表電話番号に自分で連絡し、留守電に残されていた部署名や担当者名を伝えて取り次いでもらうという方法が最も安全です。メールに記載された電話番号やリンクは絶対に信用せず、必ず金融機関の公式ウェブサイトや、口座開設時に提供された書類に記載された連絡先を利用しましょう。
結局のところ、フィッシング詐欺を見分けるためには、公式連絡先による直接確認、そしてメールやSMS内のリンクを安易にクリックしないことといった、基本に忠実な行動こそが最も確実な対策といえます。
詐欺への冷静な対応と判断
フィッシング詐欺は年々その手口が巧妙化しており、情報を盗んだ後に正規のサイトへリダイレクトするなど、被害者に気付かせない工夫が施されているケースもあります。このような詐欺に対抗するには、まず「不自然な点」に敏感であることが重要です。もしフィッシングサイトにアクセスしてしまったり、うっかりログイン情報を入力してしまったとしても、冷静に対応すれば被害を最小限に抑えることが可能です。
まずはフィッシングサイトでの操作をただちに中止し、速やかにブラウザを閉じることが第一です。その後、正規の公式サイトにアクセスし、ただちにパスワードを変更してください。そして、証券会社の公式なカスタマーサポートへ連絡し、「フィッシングサイトにアクセスした可能性がある」ことを伝え、必要な措置を仰ぎましょう。
冷静な対応こそ最大の防御
加えて、オンラインバンキングや取引履歴を定期的に確認し、もし不審な取引を発見した場合はすぐに通報する必要があります。詐欺業者は「すぐに対応しなければ危険だ」といった緊急性を強調することで、ユーザーをパニックに陥れ、冷静な判断を奪おうとします。そうした心理的な罠に陥らないよう、違和感を覚えたら一旦立ち止まり、落ち着いて行動することが何よりも大切です。
そして何より、連絡の際には必ず、メールに記載された電話番号やリンクではなく、証券会社の公式ウェブサイトや、口座開設時に受け取った書類に記載されている正規の連絡先を使用することが基本です。
このように、冷静な判断と確実な確認が、あなたの資産をフィッシング詐欺から守る最善の手段となるのです。