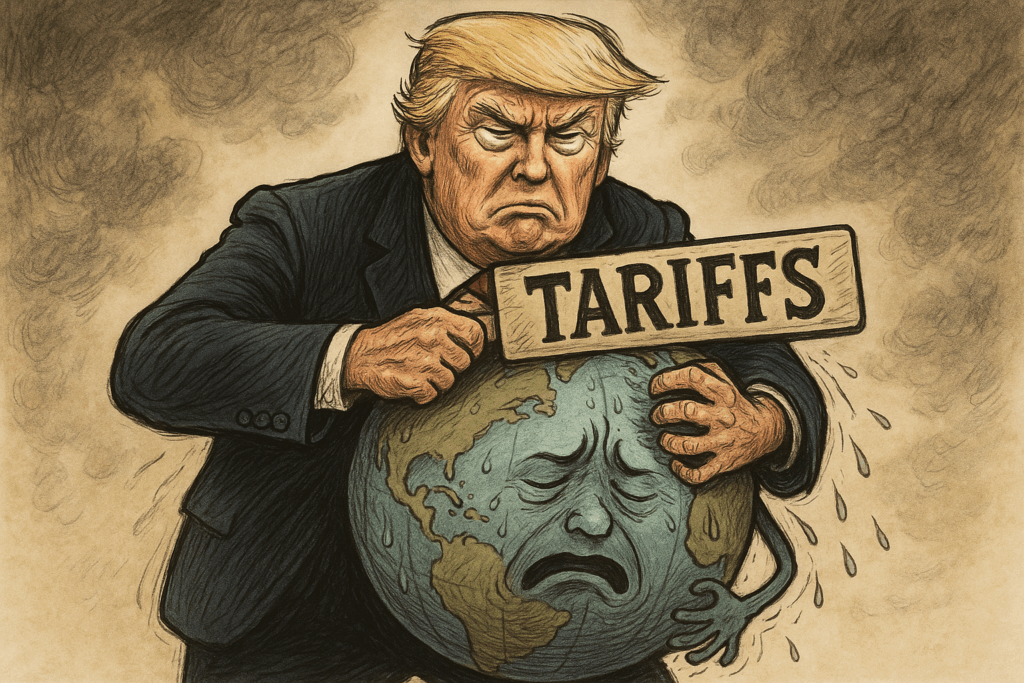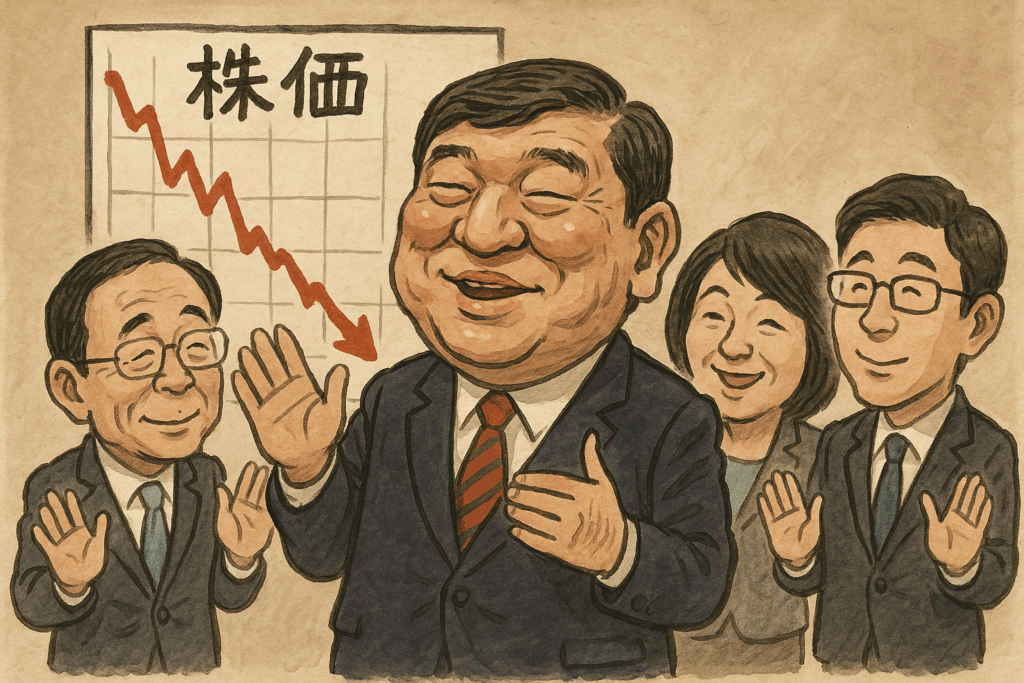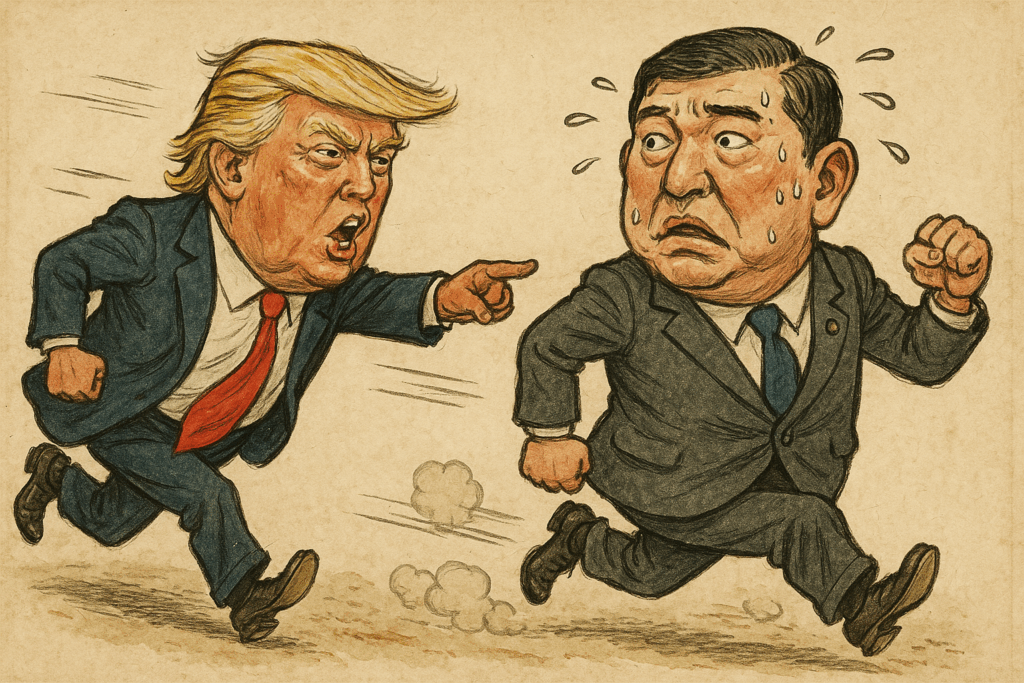2025年7月9日に終了を迎えるトランプ関税の90日猶予期間を前に、交渉は進展せず、日本政府の対応も後手に回っています。このため、週明け7月7日から市場が大きく動揺する可能性が高まっています。株価の急落や円高への警戒感が広がる中、本稿ではその背景、想定される相場の動き、最悪のシナリオ、そして投資家が今できる備えについて解説します。なお、この動画は7月6日時点の予測をもとに構成しており、最新の情報にご注意ください。
📦トランプ関税とは何か?
2025年に入り、米国のトランプ大統領は、自動車や電子部品を中心とした日本製品に対して最大24%の関税を課すと表明しました。この措置は一方的であり、米国内の製造業を保護するという政治的意図が強く、日本にとっては輸出面での打撃となりかねない内容です。
さらに、トランプ氏は交渉の過程で「30%、あるいは35%」というさらに高い関税率についても言及し、フェンタニル(麻薬対策)との関連性を示唆する発言も見られました。これは単なる経済政策というよりも、日本に対する圧力あるいは制裁の色合いを帯びており、日本の対米輸出の多くが深刻な影響を受けることが懸念されます。
🗓なぜ7月9日が重要なのか?
2025年4月3日、トランプ関税は正式に日本に通告され、90日間の猶予期間が設けられました。この期限が切れる日が7月9日であり、それにより関税措置が実際に発動されることになります。
この間、日本政府は、自動車への25%追加関税の回避を最優先課題とし、赤澤経済再生担当大臣が米国商務長官らと協議を重ねましたが、意見の隔たりは埋まらず、進展は限定的でした。農産品では米国産コメや大豆の輸入拡大案も検討されましたが、「農は国の基」として大幅な譲歩は避けられました。
さらに、在日米軍の駐留経費が交渉に持ち出され、対応を迫られたことも混乱を招きました。日本政府は、米側の要求に対し明確な合意形成には至らず、対応の不十分さが国内外で指摘されています。
📉過去の事例:2025年4月3日の急落
4月3日の関税通知を受け、市場は即座に反応しました。ドル円は約5円の急激な円高に振れ、日経平均は一時6,000円超の下落、S&P500も1,000ポイント以上の下げを記録し、世界の主要市場が一斉に動揺しました。
チャートの画面では、左上から順に、ドル円、日経225、S&P500、そしてGOLDのチャートを表示しています。特にドル円は600pips以上の急落を見せ、日経225は6,500円を超える下落、GOLDも約4万ポイントの下げ幅を記録しました。
この時期、市場はトランプ関税の発動に対し楽観的な見方も根強く、それが逆にショックを大きくした可能性があります。しかし、4月9日に90日間の猶予延長が発表されると、相場は急速に回復し、わずか数日で大きな波が形成された形となりました。
📊想定される相場の動き
7月9日の関税発動を控えた週明けの7月7日(月)は、日本市場にとって極めて神経質な展開が予想されます。日経225は、リスク回避による手仕舞いと利益確定売りが先行する形で、500〜1,000円程度の下落幅で始まる可能性があります。外国人投資家や国内機関投資家による押し目買いが下値を支える場面も見られるかもしれません。
これに米株式市場の反発が重なれば、7月8日から9日にかけて日経平均が再び3万9,000円台を回復する展開も想定されます。4月のような6,000円規模の急落はなく、調整幅としては1,000〜1,500円程度が楽観的に考える予想です。為替市場においては、初動で円高が進行し、ドル円は142〜143円台もあり得ますが、7月9日以降は144円台へ戻す可能性があり、仮に円高が進んでも2〜3円の範囲にとどまると予想されます。
🔻最悪のシナリオ:市場と実体経済の同時崩壊
もしも交渉が進展せず、トランプ関税が30%以上へと引き上げられた場合、日本の輸出企業にとっては致命的な打撃となるでしょう。輸出収益の大幅な減少が企業業績を直撃し、株価は持続的な下落トレンドへと陥る可能性があります。週明け7月7日の市場では、1,000〜2,000ポイントの大幅な下落で始まり、その動揺は中国や香港市場にも波及し、アジア全体の投資マインドを冷やすと考えられます。さらに欧州市場、そしてNY市場へとリスク回避の流れが広がり、S&P500やNASDAQも連動して下落する恐れがあります。
💱日本株・為替市場の連鎖反応と投資家心理
最悪のケースでは、4月7日に記録した31,136円に迫る水準まで株価が落ち込む可能性もあり、外国人投資家による大規模な日本株の売却がパニック的な動きを生み出すかもしれません。7月7日から9日にかけては、関税リスクと円高による影響で、外国人投資家がポジションを一斉に解消する局面も想定され、売り圧力がさらに加速する可能性があります。
円高と株安が同時に進行することで、日本市場からの資金流出が続き、国内の流動性にも悪影響を与えるでしょう。米国市場への輸出が不利になれば、企業は生産調整を余儀なくされ、特に海外展開の少ない中小企業には倒産リスクが現実のものとなってきます。世界経済が回復基調にある中で、日本だけが構造的に取り残されていると評価される事態になれば、日経平均株価が心理的な節目である3万円を割り込む展開も現実味を帯びてきます。
🧭投資家が備えるべきこと
最悪のシナリオが必ずしも現実になるとは限りませんが、市場は常にリスクを先回りして織り込みにいく傾向があります。そのため、投資家は冷静かつ柔軟な姿勢で備えることが重要です。
さらに、相場が落ち着きを取り戻した後の回復局面に備えた買いの準備を進めておくことは、投資機会の損失を防ぐ上でも有効です。
現在の株高は主に円安によって海外投資家から支えられていることも一つの要因であり、もし円安が反転し、同時に株価も下落するとなれば、海外投資家が一斉に資金を引き上げる可能性も現実味を帯びてきます。
🏛 機能不全の石破内閣がもたらす“構造的損失”
今回の関税問題は、トランプ前大統領による一方的な制裁ではなく、明確に交渉の余地を残した「ディール」である点を見逃すべきではありません。本来であれば、日本政府はこのディールに乗り、国益を守るために主張すべき場面でした。
このような結果として何の成果もない交渉は、海外投資家から見れば日本が国際社会の中で有効なパートナーとなり得ないと判断される可能性があり、投資資金は他国へと流出していきます。海外展開している大企業はダメージを回避できるかもしれませんが、国内中心の中小企業には直接的な痛手が生じ、雇用や消費にまで打撃が及ぶおそれがあります。
この状況が長引けば、日経平均株価は短期的な反発すら難しく、長期間にわたる停滞が現実のものとなる可能性があります。実際、1989年のバブル期の高値を回復するまでに34年かかったという事実は、未来の投資判断において大きな示唆を与えています。このような状況だからこそ、過度な楽観は禁物であり、あらゆるリスクに備える姿勢が今こそ求められます。