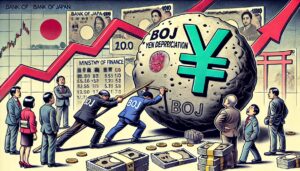2024年1月24日、日銀の政策金利引き上げ発表により、チャートは大きく動きました。リプレイチャートでその動きを再現し、金融政策の限界や政府・財務省・日銀の連携不足が与える影響を考えます。
1月24日の市場をリプレイ
チャートの左上がドル円、左下がEURJPY、中央上が日経225、中央下がS&P500、右上がビットコインUSD、右下がゴールドです。日本時間の深夜からリプレイを開始しました。
1月24日12:23、日本銀行は政策金利を引き上げる決定を行いました。この発表を受けて、金融市場では大きな変動が見られました。
ドル円のチャートを見ると、午前11時すぎに156.5円から円高へ進行し、一時的に1.5円ほど下落しました。しかし、夕方にかけては再び円安方向に戻り、最終的には156円付近で取引を終えました。一方、日経225は同時間帯に600円ほど下落し、一時的に4万円を割り込んだものの、最終的には800円ほど上昇し、40,500円付近で終了しました。
チャートを振り返ってみましょう。正式な利上げの発表は12:23ですが、11時過ぎからドル円は円高方向に動き始め、発表時刻には、大きな上下の値動きがありました。この波でドル円は、約150pipsの円高へと動きました。ユーロ円は一時円安に動いた後、円高へ転じ、軽い反発が見られました。発表前の値動きがドル円といユーロ円では若干の違いが出ていたようです。
日経225は、マーケットオープン直後から上昇トレンドが見られましたが、12:23の利上げ発表を受けて、600円ほど下げ、一時4万円を下回ったものの、その後回復し、最終的には4万円を大きく上回る水準で引けました。トランプ大統領の政策期待を背景に、S&P500は続伸しましたが、利上げの影響は限定的で、市場全体のセンチメントに大きな影響を与えなかったように見えます。
このようなリプレイ機能のある検証ツールを使えば、過去の市場の動きを振り返り、エントリーのタイミングや相場の傾向を簡単に確認できます。
日銀だけでは円安は変わらない
今回の利上げが示すように、金融政策だけでは経済の全体的な安定を図ることは難しく、政府、財務省、日銀の三者が緊密に連携する必要があります。
負のスパイラルを招く
円安が進行し、輸入コストが増加することで、原材料価格が高騰。これにより、企業の利益が圧迫され、賃金の伸び悩みが発生し、家計の可処分所得が減少。結果として、個人消費が低迷し、内需が縮小、景気の悪化を招くという悪循環が生じます。このような事態を防ぐためにも、金融政策、財政政策、経済政策のバランスを適切に取ることが不可欠です。
三者の役割
政府の役割(経済成長と内需拡大):産業政策、消費刺激策、税制改革を通じて、内需を拡大し、企業の成長をサポートする。人口減少に伴う成長の鈍化を補うため、イノベーションと規制緩和を推進。
財務省の役割(財政健全化と安定性の維持):過度な財政赤字を抑制しつつ、経済成長を妨げないようなバランスの取れた財政運営。社会保障費の増加に対応し、持続可能な財政戦略を立案。
日銀の役割(物価の安定と金融政策):インフレ目標の達成を目指し、適切な金利政策を実施。金融システムの安定を維持し、資金流動性を確保。
協力の重要性
もし、この三者の協力が不十分であれば、円安が進み、輸入物価の高騰、家計負担の増加、企業の資金繰り悪化という負のスパイラルに陥る可能性があります。金融政策の正常化は、政府と財務省の適切なサポートなしでは成功し得ません。
アベノミクスは成功だったのか?
アベノミクスは、政府、財務省、日銀が比較的協力して運営された事例の一つです。その特徴は以下の3つの矢に集約されます。
アベノミクス、三本の矢
大胆な金融緩和(異次元緩和):2%のインフレ目標に向けた積極的な資産買い入れと超低金利政策。
機動的な財政政策:インフラ投資や成長産業への財政支出。
成長戦略の推進:規制緩和、雇用改革、外国資本誘致の促進。
アベノミクスの効果
これにより、円安による輸出拡大、雇用の増加、株価の大幅上昇といった成果がありました。特に株価は、アベノミクス開始当初の水準から大幅に上昇し、投資家心理の改善にも寄与しました。しかしながら、株価の上昇は主に輸出企業や大企業が恩恵を受ける形となり、地方経済や中小企業への波及は限定的でした。
しかし、
2014年と2019年に実施された消費増税が、内需を冷やし、経済成長を鈍化させる要因となりました。
消費税増税がなければ、より高い内需拡大が期待できた可能性がありますが、財務省との協力を得るためには避けられない判断だったとも言えます。この教訓は、今後の経済政策において、適切なタイミングでの施策実行の重要性を示しています。
まとめ:利上げの効果は限定的、今後の方向性
今回の日銀の利上げの効果は限定的であり、円安の根本的な解決には至っていません。市場の動きは一時的な反応にとどまり、実質的な経済改善には三者の協力が不可欠であることが再確認されました。
金融政策のみに頼るのではなく、消費を促進する政策、中小企業への支援強化、内需の拡大など、幅広い視点からの抜本的な改革が必要であることは間違いありません。
民主主義のターニングポイント
民主主義は一つの転換点にいるとも言えます。グローバリズム、過剰な平等、平和主義が都合よく利用されています。日本国民の生活を守るため、短期的な成果にとらわれず、中長期的な経済成長を見据えた国家の運営が求められます。
今後は、政府、財務省、日銀がそれぞれの立場を超えて、自分ファーストやチャイナ・ファーストではなく、「ジャパン・ファースト」の視点で協力し、適切な政策を進めていただきたいものです。